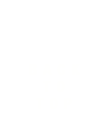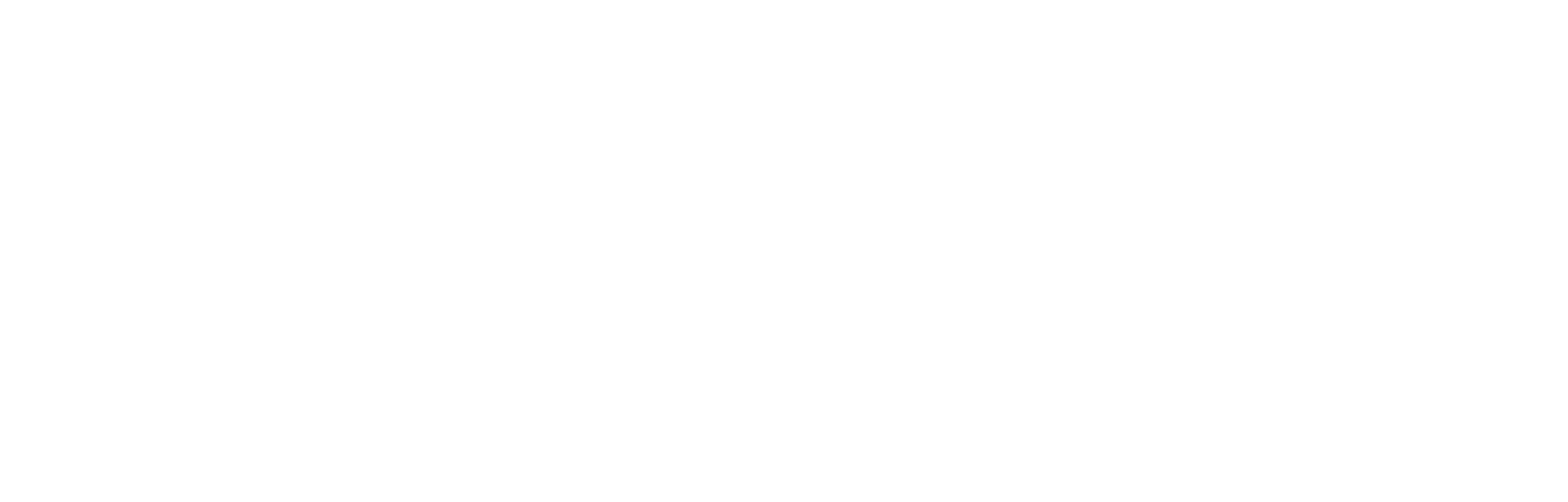
秀英舎のよもやま話~資材搬入の誇り️~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~資材搬入の誇り️~
「荷揚げ」と聞くと、重い資材を持って運ぶ仕事、というイメージが強いかもしれません。
たしかに体力は必要です。でも、荷揚げ業の本質は“ただ運ぶ”ではありません。
荷揚げ(揚重・資材搬入)は、建設現場や改修現場で使う資材を、必要な場所へ、必要なタイミングで、必要な量だけ運び入れる仕事。
つまり荷揚げがうまくいけば、職人さんはすぐ作業に入れます。
逆に荷揚げが遅れたり、置き場が間違っていたり、資材が傷んだりすれば、現場は止まります⛔
荷揚げは、現場の“スタートダッシュ”を決める仕事。
見えにくいけれど、現場にとっては心臓部です✨
この記事では、荷揚げ業のやりがいを現場目線で深掘りします
目次
1. 「現場が回る」瞬間を作れる達成感
荷揚げの最大のやりがいは、自分たちの動きひとつで現場が回り出すことです。
たとえば、内装現場なら…
-
石膏ボード
-
LGS(軽量鉄骨)
-
断熱材
-
クロス
-
床材
-
建具
-
設備機器
こういった資材を、決められたフロア、決められた部屋、決められた位置に搬入します
荷揚げがスムーズに終われば、職人さんは「待ち時間ゼロ」で作業に入れます。
現場の空気が一気に変わり、作業が動き出す瞬間があるんです。
「あ、今現場が動いた」
この感覚を肌で感じられるのは、荷揚げ業の特権です
2. “体力”だけじゃない。段取りが勝負の仕事
荷揚げは、持ち上げて運べば終わりではありません。
むしろ大切なのは段取りです。
-
資材の種類と数量を把握する
-
どこに置くか(置き場)を確認する
-
搬入ルートを確保する
-
エレベーター・階段・養生状況を読む
-
他業者と動線がかぶらないようにする
-
先に必要なものから運ぶ順番を組む
この段取りができると、同じ人数でも作業スピードが変わります⏱️✨
現場では、資材を置く場所が数十ヶ所に分かれることもあります。
その時に適当に置いてしまうと、職人さんが探す時間が発生し、二度手間になります
荷揚げが上手い人は、「運ぶ前に勝負が決まっている」くらい段取りが上手い。
頭を使う現場仕事だからこそ、成長が面白いんです
3. 職人さんからの「助かった!」が最高の報酬✨
荷揚げは、職人さんの時間を守る仕事でもあります。
時間が押している現場、タイトな工程、急ぎの材料…。そんな時ほど荷揚げの価値は上がります。
-
「早い!助かる!」
-
「ここに置いといてくれると神!」
-
「この順番で入れてくれるの分かってるね」
こういう言葉をもらえると、疲れが吹き飛びます
荷揚げは裏方に見えがちですが、実は“現場で一番感謝されやすい仕事”のひとつでもあります。
なぜなら、目の前で困っている人を直接助けられるからです✨
4. 安全に運ぶ=現場の事故を防ぐ⚠️
荷揚げで大切なのは「速さ」だけではありません。
安全が最優先です
-
腰を痛めない持ち方
-
資材をぶつけない運び方
-
角を傷つけない、壁を汚さない
-
足元や段差の確認
-
周囲の人との声かけ
-
エレベーター・階段での危険防止
現場では一歩間違えればケガにつながります。
だからこそ、無事故で終えた時の達成感は大きいです✅✨
「速くて丁寧で安全」
これができる荷揚げチームは、現場から信頼されます
5. 仕事が終わった瞬間の“爽快感”がある
荷揚げはハードな仕事です。汗もかきますし、筋肉も使います。
でも、その分だけ終わった瞬間の爽快感は格別です。
-
現場が整った
-
資材が全部所定位置に入った
-
職人さんが作業を始めた
-
今日の段取りが完璧だった
この状態で現場を後にするとき、
「今日もやり切った」
という気持ちになります
体は疲れていても、気持ちはスッキリする。
荷揚げには、そういう“現場仕事の快感”があります✨
荷揚げ業は「現場の時間」を作る誇りの仕事️
荷揚げ業のやりがいは、
-
現場を動かす達成感
-
段取りと工夫で差が出る面白さ
-
職人さんから感謝される喜び
-
安全を守る責任と誇り
-
やり切った爽快感
“運ぶ”だけに見えて、実は現場の流れを支配する仕事。
それが荷揚げ業です✨
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~「現場の時間」と「空気」を作る~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
「現場の時間」と「空気」を作る
荷揚げ業を語るとき、「きつい」「重い」「大変」というイメージが先に立つこともあります。確かに楽な仕事ではありません。でも、それだけで片付けてしまうのはもったいない。荷揚げは、現場のプロとしての価値が上がるほど、仕事が“面白くなる”世界です。
第2回では、荷揚げ業がなぜプロの世界なのか、そしてこれからの時代に必要とされ続ける理由を、さらに深く掘り下げます✨
目次
1)荷揚げは「安全を守る仕事」。事故ゼロが最大の評価⚠️
資材搬入は、常に危険が隣り合わせです。
階段で踏み外す、角でぶつける、指を挟む、腰を痛める、資材が倒れる…。現場には、事故の芽がたくさんあります
だから荷揚げのプロは、作業の中で常に安全を優先します。
-
重いものは無理して持たない(持ち方を工夫する)
-
二人持ち・三人持ちの判断を迷わない
-
階段や段差は声かけを徹底する
-
置いた資材が倒れないように安定させる
-
梱包バンドや釘、段ボールの破片を放置しない
-
養生を徹底して滑りやすさを減らす
現場で一番怖いのは「慣れ」からくる油断です。
安全を当たり前に守れる人は、どの現場でも信頼されます。
荷揚げ業は、“安全を作る仕事”でもあるんです️✨
2)資材は商品。荷揚げの品質がクレームを防ぐ
荷揚げで扱う資材は、ほとんどが“商品”です。
建具やキッチンの扉に傷をつければ交換になることもありますし、フローリングの角欠けは仕上げに影響します。電材や配管材も、置き方が悪ければ曲がったり、紛失したりします。
だからプロは「搬入=品質管理」だと理解しています。
-
角当て、毛布、養生材の使い分け
-
床材は反り防止の置き方をする
-
石膏ボードは立て掛け角度を守る
-
タイルや設備機器は衝撃を避ける
-
濡らしてはいけない資材は雨対策を徹底☔
こうした細かな配慮は、現場のトラブルを減らします。
トラブルが減れば、工程が守られ、現場の空気が良くなります。
荷揚げは、現場の“安心”を守る仕事でもあるんです✨
3)「現場の読み」ができる人ほど強い。段取りは情報戦
荷揚げのプロは、現場の情報を取りにいきます。
-
何時にどの資材が来るのか
-
置き場はどこまで使えるのか
-
どの職人がいつ入るのか
-
エレベーターの使用ルールは?
-
共用部の養生は必要?
-
近隣への配慮事項は?
この情報を先に押さえておけば、段取りは一気に楽になります。逆に、情報がないまま当日突入すると、現場で詰まりやすい。
荷揚げ業は、実は「情報戦」の側面が強いです
段取りを組むために現場を読み、相手の仕事を理解し、最適な搬入方法を作る。ここが面白いところです
4)プロになるほど稼ぎやすい理由:信頼が仕事を呼ぶ
荷揚げは、現場での評価が次の仕事につながりやすい業界です。
一度「助かった」「段取りが良い」と思われると、現場監督や職人さんは次も同じ人を呼びたくなります。
-
置き方が上手い
-
作業が早い
-
連絡が早い
-
トラブル対応が冷静
-
現場でのマナーが良い
こうした積み重ねが“指名”につながります。
指名が増えるほど、現場が安定し、仕事も途切れにくくなる。
荷揚げ業は、努力がそのまま信用として返ってくる世界です✨
5)将来性:現場がある限り、荷揚げは必要とされる️
建設業界は今後も、改修・修繕・リフォーム・インフラ更新などが続きます。新築だけではなく、既存建物の再生が増えていく時代です。こうした現場では、資材搬入の難易度がむしろ上がります。
狭い導線、居住者がいる建物、共用部のルール、近隣配慮…。
だからこそ、プロの荷揚げの価値は上がりやすい。
「現場の事情をわかっている搬入チーム」は、これからますます必要とされます✨
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~「現場のスタートを切る仕事」🏗️📦💪~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
「現場のスタートを切る仕事」🏗️📦💪
建設現場や改修工事の現場で、朝イチから慌ただしく動く人たちがいます。石膏ボード、軽天材、断熱材、床材、キッチン・ユニットバス、サッシ、配管材、電材、タイル、塗料、建具…。あらゆる資材が次々と現場に届き、それを必要な場所へ運び入れ、職人さんがすぐ作業できるように整えていく。
それが荷揚げ業です📦🚚
「荷物を運ぶだけでしょ?」と思われることもあります。ですが、現場を知る人ほど言います。
「荷揚げが上手い現場は、工期がズレにくい」
「荷揚げが段取り良いと、職人の仕事が進む」
荷揚げは“現場の時間”をつくる仕事であり、施工の勝敗を左右するほど重要な仕事なんです🔥
目次
1)荷揚げ業は「現場のスタートを切る仕事」⏱️🚪
工事は、資材が“正しい場所”に“正しい順番”で入って初めて回り始めます。
資材が一階の玄関に山積みされているだけでは、職人さんは作業を始められません。廊下が塞がれ、動線が崩れ、現場の安全も悪化します😨💦
荷揚げの仕事は、ただ運ぶのではなく、
-
どの部屋に何を入れるか(配置)📍
-
どの順番で運び込むか(段取り)🔁
-
通路を塞がない置き方(動線)🚶♂️
-
傷をつけない養生と搬入(品質)🛡️
-
ゴミや梱包材の整理(現場の空気)🧹
まで含めた「現場の立ち上げ」です。
この“最初の整い方”が、その日の作業効率を大きく左右します。だからこそ荷揚げは、現場にとって「スタートの鍵」を握る仕事なんです🔑✨
2)早いだけじゃない。「正確さ」と「気配り」が価値になる📦🤝
荷揚げの評価は、単純なスピード勝負だけではありません。もちろん早いことは大切です。でも現場で本当に喜ばれるのは、早さに加えて“正確さ”があること。
-
部屋割りが合っている(置き間違いがない)✅
-
必要な資材が取り出しやすいように置く📐
-
種類ごとに整理し、後工程が楽になる📦
-
破損や汚れを出さず、商品価値を守る🛡️
-
近隣に配慮し、騒音や共用部を汚さない🏘️
例えば、石膏ボードは角が欠けると使いにくくなります。フローリング材は小さな傷がクレームにつながります。キッチンや建具は梱包が大きく、曲がり角でぶつけるリスクが高い。
こうした資材ごとの特性を理解し、置き方・運び方を変えられるのが、荷揚げのプロです💪✨
「ただ運んだ」ではなく、「職人さんが仕事しやすいように整えた」
その差が、信頼となって積み上がります🤝🔥
3)現場で鍛えられる“段取り力”は一生モノ🧠🛠️
荷揚げの仕事は、体力勝負に見られがちですが、実は“頭を使う仕事”です。
現場には毎回条件が違います。
-
階段しかない物件
-
エレベーターが使えない時間帯
-
通路が狭く、曲がり角が多い
-
既存の家具や設備がある改修
-
住民がいるマンションでの搬入
-
雨の日で足元が滑りやすい
こうした条件の中で、最短で安全に、しかも資材を傷つけずに搬入するには、段取りが必要です。
-
先に大物を入れるか、先に軽い物を入れるか
-
通路を確保しながら搬入する順番
-
置き場の確保と仮置きの判断
-
人数配置(誰が先導、誰が受け取り、誰が養生)
-
体力配分(最初に飛ばしすぎない)
これを毎現場で組み立てていくうちに、段取り力が自然と鍛えられます🔥
この力は、どんな現場仕事にも通用します。だから荷揚げは、「現場で生きていくための基礎体力と基礎思考」が身につく仕事でもあります😊
4)チームワークの気持ちよさ。息が合うと“現場が流れる”🤝🏗️
荷揚げは、チームでやるほど真価が出ます。
声かけ、合図、リレー搬入、置き場整理、養生。誰か一人が勝手に動くと、ぶつかったり、資材を落としたり、通路が塞がれたりします。
だからこそ、
-
「次、ボード行きます!」📣
-
「右曲がり角注意!」⚠️
-
「この部屋、先に床材置こう」
-
「この通路空けておこう」
こうしたコミュニケーションが大切になります。
息が合うチームは、搬入が“流れるように”進みます。テンポよく、ムダなく、安全に。
現場監督や職人さんが「今日は早いな」「助かるわ」と言ってくれる瞬間、チーム全体の達成感が一気に高まります🔥✨
5)「ありがとう」が直で返ってくる仕事😊✨
荷揚げの良さは、評価が分かりやすいこと。
作業が終わった直後に、職人さんの反応が返ってきます。
-
「置き方めっちゃ助かった!」
-
「通路が空いてるから作業しやすい!」
-
「今日は段取り良かったな!」
-
「また次も頼むわ!」
この“現場での信頼”は、数字や書類ではなく、目の前の言葉で返ってきます。
体を動かして、現場を整えて、人の役に立つ。そういう仕事をしたい人にとって、荷揚げ業はやりがいの塊です💪✨
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~荷揚げ業が変わる!~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~荷揚げ業が変わる!~
荷揚げ業界は今、労働環境の改善・機械化・施工スピードの向上などにより大きく変化しています。
特に都市部の大型建設現場では“荷揚げの質”が工程全体を左右する時代です。
ここでは、 現場の課題・最新の搬入技術・労働改善・今後求められるスキル を深く解説します。
目次
■ 荷揚げ業の現場課題とは?
① 作業の「重労働化」
石膏ボードは一枚20〜35kg。
LGSは長く、束になると非常に重い。
設備機器は50〜100kg以上。
職人への身体的負担は大きいのが現実です。
② 現場の時間制限
搬入できる“搬入可能時間”が厳しく決められている現場が増えており、
短時間で確実に終わらせる技術が求められます。
③ 他職との干渉
電気、設備、内装、外装など多くの職人が同時に作業しているため、
衝突・動線の被りによるリスクも増えています。
④ 物量の増加
高層建築・大型施設では、運ぶ物の量が桁違い。
荷揚げ屋の段取り次第で工事全体の効率が変わります。
■ 荷揚げの世界を変える“効率化の最新技術”⚙️
現場は今、確実に進化しています。
■ ① 電動アシスト台車・パワーアシストスーツ
重い資材も少人数で運べる時代へ。
-
腰の負担軽減
-
階段でのサポート
-
包丁材や建具の持ち運びがスムーズに
「人力×機械」の組み合わせが主流になりつつあります。
■ ② ホイスト・モノレールの高性能化
高層階への搬送スピードが劇的にアップ。
-
自動停止
-
過重量センサー
-
落下防止機構
安全性が飛躍的に進化しています。
■ ③ 資材仕分けアプリ
搬入担当・原価管理・現場監督が連携できるアプリが増加。
-
搬入量
-
仕分け場所
-
搬入時間
-
材料種類
-
作業完了報告
が一目でわかり、搬入ミスが激減。
■ ④ 建設用エレベーター(工事用EV)の進化
広さ・容量・速度が向上し、荷揚げ効率が大幅アップ。
■ 荷揚げ業の“安全対策”が重要視される理由⚠️
荷揚げは重労働で危険も伴うため、安全対策が業界全体で強化されています。
-
足元養生
-
階段の滑り止め
-
転倒防止の縛り
-
声かけのルール化
-
資材置き場のゾーニング
-
作業半径の確保
「安全が確保できる段取り」を作れるのがプロの荷揚げ職人です。
■ 次世代の荷揚げ職人に求められるスキル️
◆ ① 動線改善のセンス
どの順番で、どのルートで運ぶべきか瞬時に判断できる力。
◆ ② 資材知識
石膏ボード・建具・配管・木材・住設…
種類を知ってこそ最適な持ち方ができる。
◆ ③ チームワーク
“荷揚げはチームの質で決まる”と言われるほど重要。
◆ ④ 肉体管理
体が資本。
ストレッチ・食事・筋トレ・休息も含めたセルフケアが必須。
◆ ⑤ ITリテラシー
アプリ報告・QR管理・電子指示書が増えているため、今後は必須スキル。
■ 荷揚げ業の魅力✨
-
終わった時の達成感が圧倒的
-
現場がスムーズに進むのは自分たちのおかげ
-
職人から頼られる存在
-
運動好きには最高の仕事
-
チームでやり遂げる楽しさ
何より、建物が完成していく瞬間に立ち会える誇りがあります。
■ まとめ
荷揚げ業は過酷な面もありますが、同時に技術・段取り・連携・安全意識のすべてが問われる“専門職”です。
建設現場の最初の工程を支える、なくてはならない存在。
そして今、最新技術の導入によって大きく進化し始めています。
これからの荷揚げ職人は、
「人の力×機械の力×知識」 を組み合わせた、よりスマートで強いプロ集団へと変わっていくでしょう✨
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~“荷揚げ職人”~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~“荷揚げ職人”~
建設現場で作業を見ていると、材料が次々と高層階へ運ばれていく光景を目にします。
石膏ボード、フローリング材、軽量鉄骨材(LGS)、配管、サッシ、建具、設備機器…。
しかし、それらを 「どうやって」「誰が」「どのような手順で」 運び込んでいるのか、一般の人はほとんど知りません。
その裏側には必ず、
“荷揚げ屋(荷揚げ職人)”の存在があります。
彼らは建設のスピードと安全を支える、いわば“影の立役者”です💪🔥
ここでは、荷揚げ業の仕事の流れ、必要な技術、安全管理、現場での判断力、チームワークの大切さまで、専門的に深く解説します。
目次
■ 荷揚げ業とは?📦💨
荷揚げ業とは、建設現場へ搬入される 重量物・長尺物・資材 を、指定された階・部屋・場所まで運び込む専門職です。
取り扱うものは多岐にわたり…
-
石膏ボード(12.5mm・15mm)
-
LGS(軽量鉄骨)
-
フローリング
-
巾木
-
内装建材
-
住設(ユニットバス、キッチン、洗面台)
-
サッシ
-
空調機器
-
太陽光パネル
-
タイル・石材
-
防火材
-
各種設備配管
-
コンパネや長尺材
など、“建物に必要なほぼすべての材料”が対象です。
重量物だけでなく長い材料も多く、
持ち方・運び方・角の回し方・養生の工夫など、非常に高度な技術が求められます。
■ 荷揚げ職人の“一日の流れ”⏰💼
◆ ① 朝礼・KY(危険予知)
現場の監督や他の職種と連携し、安全ポイントを共有します。
-
今日の動線
-
クレーンの使用有無
-
ホイスト・モノレールの稼働状況
-
他職との作業干渉
-
天候や滑りリスク
これらを把握してから作業開始。
◆ ② 資材の搬入トラック到着🚚
ドライバーと指示書を確認し、積み荷をチェックします。
荷崩れ防止、数量確認、傷がないかを確認しながら、
搬入ルートに合わせて資材を組み替えることも。
ここがすでに“プロの段取り力”です。
◆ ③ 建物内への搬入開始🏗️💪
建物内へ資材を運び込みます。
-
階段搬入
-
エレベーター(工事用)
-
ホイスト・モノレール
-
手運び
-
台車搬送
-
クレーン吊り上げ
現場により環境はさまざま。
荷揚げ屋は状況に応じて最適な搬入方法を瞬時に判断します。
◆ ④ 各部屋・各階へ仕分け📦🏢
職人が作業しやすいよう、
“どの材料を・どこへ・どの順番で” 置くかを考えます。
石膏ボードひとつでも、
-
ロング
-
レギュラー
-
耐火
-
防音
-
天井用
など種類は多く、間違えると工期に影響します。
◆ ⑤ 養生・破損防止対策🧰
資材に傷をつけないのは当然ですが、建物の壁や床も守らなくてはいけません。
-
コーナー養生
-
養生シート敷き
-
養生テープ
-
角材で浮かせる
-
スペース確保
荷揚げの質は、「傷をつけずにキレイに終われるか」で決まると言っても過言ではありません。
◆ ⑥ 重量物の運搬💪🔥
ユニットバス、室外機、石材、大型設備など重量物は、2〜6人のチームで運搬します。
声かけが命で、
-
「いくよ!」
-
「よいしょ」
-
「下ろすよ!」
-
「せーの!」
などの掛け声でリズムを合わせ、怪我を防ぎます。
◆ ⑦ 最終確認・清掃🧹
最後に周辺の清掃、資材の転倒や散乱がないかをチェック。
荷揚げ屋は 「運んで終わり」ではなく、「安全に現場を仕上げて終わり」 が仕事なのです✨
■ 荷揚げ職人に必要な“高度な技術”とは?🛠️🔥
🔸 ① 資材の持ち方
石膏ボードは風に弱く、腰を痛めやすい材料。
LGSは長尺で曲がりやすい。
建具は傷が命取り。
種類によって持つ位置・角度が異なります。
🔸 ② 動線の読み取り
狭い廊下・階段・カーブ。
先にどの材料を通すかで効率が変わる。
これが“段取り力”。
🔸 ③ チームワーク
声かけ、テンポ合わせ、役割分担。
荷揚げは1人では成立しない仕事。
🔸 ④ 体力管理
毎日がトレーニング。
食事・睡眠・ストレッチ・筋トレも実務のうち。
🔸 ⑤ 安全管理
作業の8割は“危険予知”で決まると言われるほど。
-
つまづき
-
転倒
-
角当て
-
指挟み
-
資材倒れ
常にリスクを読みながら作業を進めます。
■ 荷揚げ業の魅力✨
荷揚げの最大の魅力は、
建物ができていく過程に一番近い場所で仕事ができること。
-
自分が運んだ材料で建物ができていく
-
現場から頼られる存在
-
達成感がダイレクトに味わえる
-
チームで完成を目指すワクワク感
身体はキツいけれど、それ以上に誇りのある仕事です😄🔥
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~可視化・改善・サステナで現場を進化させる📱📊♻️~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~可視化・改善・サステナで現場を進化させる📱📊♻️~
デジタルと改善の小ワザで「遅れない・壊さない・待たせない」を実現する方法を、具体ツールと運用例でまとめます。大がかりなシステムなしでも、写真・QR・チャット・テンプレの組合せで驚くほど現場は変わります。🚀
目次
- 1 1️⃣ 可視化の第一歩は“写真+時刻+場所”📸🕒📍
- 2 2️⃣ QRで“取り違いゼロ”——資材と置場を紐づける🏷️🔗
- 3 3️⃣ チャットOps:電話の取りこぼしをゼロに📲🧑💻
- 4 4️⃣ 配車と便割りの“余白”を設計する🧮🗓️
- 5 5️⃣ ミスは前日に潰す——“3点セット”の前日BM(ブリーフィング)🗺️✅
- 6 6️⃣ 物理の“定石”で荷崩れゼロ📐🧲
- 7 7️⃣ 狭隘・上層・長尺の“難所”攻略🧭🏗️
- 8 8️⃣ トラブル対応テンプレ——“報告→判断→再開”の3手🧯🧠
- 9 9️⃣ サステナブル搬入——静かに強い競争力♻️🌿
- 10 🔟 人が辞めないチームの作り方——採用・教育・評価👷♀️👨🏫🏅
- 11 1️⃣1️⃣ ケース:商業施設の什器1,000点・2夜で完了した理由🛍️🌙
- 12 1️⃣2️⃣ 明日からできる“小さなDX”リスト🛠️✨
- 13 まとめ:荷揚げDXは“段取りの質”を底上げする道具🧩🚦
1️⃣ 可視化の第一歩は“写真+時刻+場所”📸🕒📍
-
積込写真:荷姿・ラッシング・番号。
-
到着写真:ゲート・養生状況。
-
設置写真:フロア図と一緒に仮置き状態を撮影。
すべてに時刻と場所を自動刻印して共有。責任分界の明確化と改善の種が一度に手に入ります。💡
2️⃣ QRで“取り違いゼロ”——資材と置場を紐づける🏷️🔗
-
入荷シールにQR(品名/数量/階/ゾーン)。
-
読み取り→置場ラベル印刷→棚札貼りで、**“この山は誰の何枚”**が一目瞭然。
-
棚卸もスマホでピッと。不足・余剰を朝の5分で把握。
📈副産物:欠品・誤納のパターンが数値化され、再発防止の議論が“感覚論”から解放されます。
3️⃣ チャットOps:電話の取りこぼしをゼロに📲🧑💻
-
グループ:元請・内装・設備・電気・搬入・警備の混成。
-
固定フォーマット:「階/ゾーン/品目/数量/希望時刻/制約」。
-
通知ルール:“変更は赤字”、“確定は✅”。
📣効果:**「10:00→10:30へ」**が瞬時に共有され、便割り・人員の再配分が即時に。
4️⃣ 配車と便割りの“余白”を設計する🧮🗓️
-
基準ダイヤに10〜15分のバッファ。
-
便間隔は短く詰めない。30分以上のクッションで事故を防ぐ。
-
混乗禁止(階混在)を徹底し、降ろし混乱を消す。
🧭心得:「“詰める勇気”より“空ける覚悟”」。結果的に全体が速くなります。
5️⃣ ミスは前日に潰す——“3点セット”の前日BM(ブリーフィング)🗺️✅
-
搬入経路図(高さ制限・狭幅員・段差)
-
階別配置図(仮置きレイアウト)
-
資材一覧(寸法・重量・天地無用)
17時までに5分オンラインで確認。写真1枚で現場の“想像不足”を解消します。🎯
6️⃣ 物理の“定石”で荷崩れゼロ📐🧲
-
上締めだけでは滑る:摩擦係数0.4の床で横加速度0.5g想定。対向締めを併用。
-
角当て+ゴムで剪断に強い面を作る。
-
台木は同材・同寸でペア。高さ差は“割れ”を呼ぶ。
-
増し締めトリガ:出発10分後/高速進入前/雨後。
🧱結果:搬入起因の欠け・割れが目に見えて減ります。
7️⃣ 狭隘・上層・長尺の“難所”攻略🧭🏗️
-
曲がり角:内輪差シミュレーションをタブレットで可視化、同じ画面を誘導員と共有。
-
段差:鉄板+ゴムでなだらかスロープ。モノは壊さず人も楽。
-
長尺:先頭・中間・後尾で**“3点保持”**、掛け声で歩調を合わせる。
-
上層階:ELV待ちを階段搬送チームで吸収。交互運用で待機ゼロへ。
💬合図:「いきます」「どうぞ」「止め」——短く、全員が同じ言葉で。
8️⃣ トラブル対応テンプレ——“報告→判断→再開”の3手🧯🧠
-
破損発見:触らず写真→位置特定→共有→原因仮説→置場分離。
-
遅延:代替動線(階段・別ゲート)で再計画、後続便へ即通知。
-
人員不足:隣接階から融通、昼休みのシフト前倒し。
📌大事:沈黙が一番のロス。小さな遅れも即報告が正義です。
9️⃣ サステナブル搬入——静かに強い競争力♻️🌿
-
リターナブル養生材(角当て・ゴムマット)を回収箱で循環。
-
アイドリング5分ルール+定速走行で燃費改善。
-
資材ゴミ分別:パレット・PPバンド・発泡スチロールを現場内で分ける。
-
静音キャスター/防振マットで夜間苦情ゼロへ。
🌱見える化:月報にCO₂削減量(推定)と再利用率を載せると、入札と採用に効きます。
🔟 人が辞めないチームの作り方——採用・教育・評価👷♀️👨🏫🏅
-
採用:現場の“社会的意義”を語る。**「あなたが運んだ資材が病院の一室になる」**は強い動機。
-
教育:1日目は成功を設計(軽量→中量→重量の順)。
-
評価:無事故・報告の速さ・改善提案をポイント化。
-
家族向け現場見学で理解者を増やす。
🌟文化:「ありがとう」を可視化(日報に“称賛欄”)。現場は褒め合うほど速く、強くなります。
1️⃣1️⃣ ケース:商業施設の什器1,000点・2夜で完了した理由🛍️🌙
-
施策:QRラベルで売場番号=置場を紐づけ、売場マップを全員のスマホへ。
-
運用:先行便で通路養生+サイン設置、本隊はワンウェイ動線で逆走ゼロ。
-
結果:待機ゼロ/破損ゼロ/開店前仕上げ完了。ポイントは**“現場全員が同じ地図”**でした。
1️⃣2️⃣ 明日からできる“小さなDX”リスト🛠️✨
-
置場に**A3の“今日の完成図”**を貼る。
-
ELV待ちは**“今の待ち時間”**をホワイトボードで見える化。
-
転倒リスク2m以内は赤テープで囲う。
-
手指・声のサインを3語だけに統一する。
-
終業5分の振り返りで「良かった1つ/直す1つ」を必ず出す。
どれも無料 or 低コスト。でも効果は絶大です。
まとめ:荷揚げDXは“段取りの質”を底上げする道具🧩🚦
アプリやQRは目的ではなく、段取り・安全・品質を強くするための手段。可視化→共有→即断のサイクルを回せば、現場は遅れず・壊さず・待たせずに前進します。荷揚げは今日も、明日の出来形をつくっている——現場を進める最初の歯車として、私たちはもっと誇っていい仕事をしています。💪
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~段取り・安全・品質で現場を前に進める️~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~段取り・安全・品質で現場を前に進める️~
建築・内装・設備の工事現場では、資材が「必要なときに・必要な場所へ・必要な姿で」届くことが品質と工期の大前提です。荷揚げ(揚重)は、その前提を支える縁の下の力持ち。石膏ボードや軽量鉄骨、配管・空調機、サッシ、床材、什器、OA機器……重量物から繊細な高額機器まで、搬入→水平移動→垂直搬送→各階仮置き→仕分け→集積を一気通貫でこなします。今回は、荷揚げ業の実務を「段取り・安全・品質」の三本柱で深掘りし、現場で“今日から効く”具体策をまとめます。
目次
- 1 1️⃣ 仕事は発注を受けた瞬間から始まる——情報の骨組みづくり️
- 2 2️⃣ デリバリー設計——トラック便割りと“ラスト10m”の設計
- 3 3️⃣ 養生と保護——傷をつけない準備が最速の近道️
- 4 4️⃣ 垂直搬送の選択——エレベーター/マスト/チェーンブロック♂️️
- 5 5️⃣ 水平移動の科学——台車・ハンドリフト・ミニクローラ
- 6 6️⃣ 仮置きと仕分け——“使いやすい山”を作る️
- 7 7️⃣ 安全の型——KYT・TBM・指差し称呼
- 8 8️⃣ 品質は“運び終わってから”評価される——外観・数量・配置
- 9 9️⃣ 事例:石膏ボード1,200枚・夜間搬入・12F案件の勝ち筋
- 10 人材の力——“速さ×再現性×安全”で評価する
- 11 まとめ:荷揚げは“現場を進めるプロジェクトマネジメント”
1️⃣ 仕事は発注を受けた瞬間から始まる——情報の骨組みづくり️
-
資材情報:品目・数量・寸法・重量・梱包形態(パレット/バラ/長尺)・天地無用/横倒し禁止などの条件を確定。
-
現場条件:搬入動線、ゲートサイズ、エレベーター台数と積載、階段有無、クレーン・マストの可否、養生範囲、騒音・時間帯制限。
-
工程接続:内装・設備・電気の作業予定と干渉を洗い出し、“どの階の・どのゾーンへ・何時までに”を秒単位で落とし込みます。
コツ:発注元に「品目別の“最小割り付け単位”」を聞き出す(例:石膏ボードは“1区画=30枚”など)。置き場過多や不足を防げます。
2️⃣ デリバリー設計——トラック便割りと“ラスト10m”の設計
-
便割り:混載せず「階別」「ゾーン別」に分便。早着・遅延の揺らぎを吸収するため、先行便は軽めに、後続便は調整枠に。
-
ラスト10m:ゲート〜仮置きまでの床レベル差、スロープ角、扉の有効幅、突起物。**“ドアノブ1本の出っ張り”**が動線を殺すことも。
-
待機所:近隣への騒音配慮と駐停車ルールの事前合意。警備会社とも連携して“詰まり”をゼロに。
ポイント:「先に降ろす順」=「荷台で最後尾」。積み順を現場の置場順へ反転設計します。
3️⃣ 養生と保護——傷をつけない準備が最速の近道️
-
床:コンパネ+ノンスリップマットで二層。曲がり角は耳当てを追加。
-
壁・開口:角当てコーナー、支柱式プロテクタ。ドアは外して保管するか、仮蝶番でフルオープン化。
-
養生の色分け:共用動線は青、資材置場は緑、危険部は赤など視覚ルールで事故を減らす。
✨効果:養生の“上質感”はそのまま元請・施主の信頼に直結。写真記録も忘れずに。
4️⃣ 垂直搬送の選択——エレベーター/マスト/チェーンブロック♂️️
-
荷物用ELV:積載・内法・かご高さ・床耐荷重を計測。偏荷重禁止、養生板のたわみにも注意。
-
マストクライマー:外壁足場と干渉しない計画と風速基準。夜間は作動停止ルール徹底。
-
チェーンブロック/チルホール:小規模改修や階段のみ現場の切り札。吊点の構造確認と二重掛けが鉄則。
️風対応:外部揚重は風速10m/sで中断基準。タグライン併用で振れ止め。
5️⃣ 水平移動の科学——台車・ハンドリフト・ミニクローラ
-
台車の車輪径=段差×4が目安。静音ゴムで夜間騒音を削減。
-
ハンドリフト:パレットものは差し込み方向を統一し、ピボット回転の余地を確保。
-
ミニクローラ:重量機器の室内搬入で活躍。床養生は荷重分散板を必ず。
人の動き:押す>引くが基本。背面確認員を置けば接触事故が激減。
6️⃣ 仮置きと仕分け——“使いやすい山”を作る️
-
先使い手前、後使い奥。ラベルは“廊下側”に向ける。
-
積み高さ:胸下(1,000〜1,100mm)を上限に。高積みは倒れリスク増。
-
ボード:同一ロットで1山。色味差混在は後の手直しを生む。
-
配管・ダクト:曲げ半径を守る枕木配置。
証跡:置場完成ごとに写真+配置図を共有。後工程との“場所取り”揉め事を撲滅。
7️⃣ 安全の型——KYT・TBM・指差し称呼
-
朝礼でKYT(危険予知):落下・挟まれ・つまづき・過荷重を具体化。
-
TBMは各タスク開始前に3分:役割・動線・合図を即共有。
-
指差し称呼:「手元良し、足元良し、上良し、周囲良し!」。声が現場のテンポを整える。
熱中症対策:WBGT計測・塩タブ・日陰ローテーション。無理をしない勇気が命を守る。
8️⃣ 品質は“運び終わってから”評価される——外観・数量・配置
-
外観:傷・角欠け・箱つぶれを荷卸直後にチェックし相互確認。
-
数量:指差し読み上げと二重チェック、差異は即連絡。
-
配置:施工手順の流れに沿って“次に手に取る順”で並べる。
報告:完了時はフロア図+写真+不足・破損リストを即送信。**“報告の速さ=信頼”**です。
9️⃣ 事例:石膏ボード1,200枚・夜間搬入・12F案件の勝ち筋
-
条件:荷ELV1基、近隣騒音厳しめ、0:00〜5:00。
-
設計:先行便は雑材・養生材、2〜4便で階別パレット、最終便に予備+不足吸収。
-
成果:待機ゼロ/苦情ゼロ/翌朝の内装工“即着工”。鍵は先行養生と階別ラベル、便間隔の固定でした。
人材の力——“速さ×再現性×安全”で評価する
-
新人教育:まずは台車と養生。1日で成功体験を。
-
ベテランの暗黙知を動画SOP化(30秒×1工程)。
-
評価は“速さ”だけでなく再現性と無事故を重視。
文化:挨拶と報連相の“当たり前”が、クレームを未然に消します。
まとめ:荷揚げは“現場を進めるプロジェクトマネジメント”
段取りで渋滞を消し、養生でクレームを消し、合図で事故を消す。荷揚げは単なる運搬ではなく、工事全体の歩調を整える仕事です。今日の一便が、明日の出来形を決める。正しく速く、そして美しく——それが現場が求める荷揚げの価値です。
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~変遷~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~変遷~
“運ぶ”から“現場のスループットを設計する”仕事へ ️
建設現場の当たり前——必要な資材が、必要な階・必要な数・必要な時間に並んでいること。
この当たり前は、荷揚げ(揚重・資材搬入)の段取り力で成り立っています。ここ10〜20年で現場環境は大きく変わり、荷揚げ業者に求められる役割も運ぶ人から工程を前に進める人へと進化しました。本稿では、時代の変遷を振り返りながら、いま現場が荷揚げに求める中核ニーズを整理し、すぐ使える実装アイデアまで落とし込みます。
目次
1|時代の変遷:荷揚げの“当たり前”はこう変わった
① アナログ大量搬入 → JIT・細分化搬入(半日スロット)⏱️
-
以前:仮置き場に“まとめてドン”。現場は置場広く、工程も緩め。
-
いま:都市部の狭小現場・短工期が一般化。30〜60分の時間窓でエレベーターやクレーンを共用、午前○セット/午後○セットのジャスト・イン・タイムが標準に。
② 人海戦術 → マテハン・安全標準化
-
以前:体力勝負、属人的。
-
いま:台車・ハンドリフト・階段昇降機・簡易リフト・荷揚げロボの活用、合図・ゾーニング・養生の標準化で“軽く・安全に”。
③ 口頭連絡 → デジタル同期(ETA/ePOD/フロアマップ)
-
以前:電話と紙伝票。
-
いま:到着予測(ETA)共有、電子受領(ePOD:写真・個数・位置)、フロア別配置図のクラウド共有で“待ち”と“探し物”を削減。
④ 一括請負 → 多職種インターフェース
-
以前:運ぶ=完了。
-
いま:内装・電気・設備・サッシなど各職種の作業順まで踏み込み、「どの順に並べれば今日の生産性が上がるか」を設計。**“置き方の質”**が評価対象に。
⑤ 労務規制の強化 → 中継・スロット・待機課金の明確化 ⚖️
-
長時間拘束の是正に伴い、中継輸送・時間窓厳守・待機時間の可視化が進行。“無理やりどうにか”の余地は縮小、契約と運用の設計力が差に。
2|いま現場が求める核心ニーズ(5本柱)
1) 時間の正確さ:待たせない段取り
-
スロット予約(クレーン・搬入路・EV占有)
-
ETA共有でクレーン・職種と時間で合流
-
差し込み枠を1日数本確保して“急ぎ”に即応
2) 安全とコンプライアンス:ゼロ事故の証跡
-
合図者の明確化、吊荷下立入ゼロ、立入禁止のゾーニング
-
養生・角当て・バンドのSOP(写真つき手順)
-
点検・KY結果を写真+タイムスタンプで残す
3) 品質(ダメージゼロ):置き方が生産性を決める
-
先入れ先出し、曲げ・反り防止、作業順に合わせた並べ替え
-
階段上げの人員配置や**中継置場(バッファ)**の設計
-
**“翌日の1手目が軽くなる”**配置図
4) トレーサビリティ:数・場所・状態の見える化
-
ePOD(数量・ロット・配置場所・傷の有無)
-
フロアごとの配置マップ共有(スマホ)
-
クレーム時の因果切り分けが即日で可能
5) サステナ&コスト:ムダ歩きゼロ/再利用前提
-
リターナブル養生・台車共用化、空搬送の削減
-
搬入→バラシ→回収までの往復設計
-
KPIはOTIF(時間内・数量内達成)×損傷率×待機時間で評価
3|“価値提案”としての商品化(そのまま使える型)
A. OTIF保証パック(時間と数量の約束)
-
到着時間±15〜30分/数量100%/配置完了時刻をKPI化。
-
超過時は待機課金・代替車手配SLAでフェイルセーフ。
B. ダメージゼロ&作業効率パック
-
養生仕様・角当て・台車種の標準化、作業順配置図の提出。
-
翌日の**“1手目短縮時間(min)”**をレポート。
C. デジタル同期パック
-
ETAダッシュボード+ePOD+配置マップをまとめて提供。
-
監督・職長が**スマホで“どこに何枚”**を即確認。
4|現場で効いたミニ事例(ショートケース)
-
タワマン内装期/ボード200枚/フロア
-
Before:EV渋滞→大工手待ち多発。
-
After:30分スロット+各戸バッファ+矢印養生。
-
効果:1フロア完了が**−90分**、損傷率ほぼゼロ。
-
-
オフィス改修/夜間限定
-
Before:搬入路が狭く騒音クレーム。
-
After:静音キャスターと養生材変更、台車待機列の視覚化。
-
効果:クレームゼロ、搬入本数**+15%**。
-
5|受入条件チェックリスト(合意すると強い)✅
-
搬入時間窓/クレーン・EVの占有スロット
-
搬入ルートの幅・高さ・曲がり半径
-
仮置き可能スペース(中継置場)の有無・サイズ
-
養生基準(床・壁・角)と静音要件
-
合図者・連絡先、気象限界(風・雨・雪)
-
待機課金・代替手配・順延のルール
6|90日でできる“ニーズ対応”ロードマップ️
0–30日
-
積込み・養生・搬入・配置の**写真つきSOP(A4×3枚)**を作成
-
スロット予約表と配置図テンプレを標準化
31–60日
-
ETA共有+ePOD運用開始(無料ツールでもOK)
-
主要3現場で**中継置場(バッファ)**を試験導入
61–90日
-
OTIF×損傷率×待機のKPIレポートを月次化
-
監督向けに**“受入条件シート”**の合意運用を開始
7|これからの変化に備えるヒント
-
ユニット化・大型化:一度の揚重で“置き切る”設計が増加 → 搬入路・回転半径の事前検証が鍵。
-
夜間・静音ニーズ:商業ビル改修が増加 → 静音キャスター・低騒音機材・照度計画をパッケージ化。
-
人手不足:多能工化と道具の自動化(昇降機・簡易リフト)で“軽く・速く・安全に”。
-
環境配慮:リターナブル梱包・台車リースの共同化、搬入計画のCO₂可視化が評価指標に。
結び――“運ぶ”から“前に進める”へ
荷揚げの価値は、時間・安全・品質・証跡・環境の五角形で決まります。
段取りが良ければ現場は速く、安全は上がり、コストとCO₂は下がる。
運ぶ人から現場のスループットを設計する人へ。
この視点を持つ荷揚げ業者から、指名と信頼が集まります。次の現場でまずは、スロット予約・ePOD・配置図の三点を。
“待たせない・壊さない・止めない”を、チームの新しい標準にしていきましょう。✨
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~「荷を上げる」の先にあるもの~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~「荷を上げる」の先にあるもの~
マンションやオフィスビルの建設現場で、石膏ボード、サッシ、フローリング、設備機器…重くて嵩張る資材が、“必要な階に、必要な数だけ、必要な時間に”並んでいる。
その“当たり前”を支えるのが荷揚げ(資材搬入・揚重)です。スポットで呼ばれることも多い仕事ですが、現場全体の出来に直結する“影の司令塔”。ここには他の職種にはない手応え=やりがいが詰まっています。
目次
1|「時間を設計する」快感 ⏱️
荷揚げは工程の起点。ラフター・タワークレーン・荷捌き・ハンドリフト・資材置場…多くの歯車を噛み合わせ、遅れゼロで回す段取りはパズルを解くみたいに面白い。
-
30分幅のスロットでクレーン共用を調整
-
エレベーター占有を階ごとにローテ
-
「先にボードを立て込む→後で配線」など職種間の最短路を引く
組んだ段取りどおりに現場が動いた瞬間、静かなガッツポーズが出ます。
2|“目に見える成果”が毎日残る
朝は空っぽだったフロアが、昼には壁材の山が番号順に整列、夕方には翌日の作業動線まで確保。
写真1枚で達成度が分かるのがこの仕事の醍醐味。職長や監督からの「助かった!」は何度聞いても嬉しい。
3|安全をつくる誇り
荷崩れ・指はさみ・転倒・飛来落下…現場事故の多くは搬入の質に左右されます。
-
結束・荷重分散・角当ての基本
-
通路幅・段差・勾配の事前確認
-
**“吊り下の立ち入りゼロ”**の徹底
「何も起こらなかった一日」が最高の成果。安全を設計する仕事でもあります。
4|体力だけじゃない、“運ぶ技術”
同じ200枚の石膏ボードでも、置き方・向き・順番で大工の生産性が激変。
-
階段上げの人員配置(上2・下1など)
-
平台車+養生で床を守りつつ最短動線
-
先入れ先出しで曲げ・反りを防止
「重いものを持つ」から「軽く運べる段取り」へ。技術介在の余地が大きい。
5|多職種と“つながる”一体感
電気・空調・内装・防水・左官…すべての職種が、荷揚げの質とタイミングに乗って仕事を始めます。
「何時までに何セット並べる?」「この順でいい?」と短い会話で現場がスムーズに流れたとき、袖で現場を回している感覚が得られます。
6|現場改善が目に見えて効く
荷姿が崩れやすい、搬入口が狭い、搬送距離が長くて人がバテる…そんな“現場の痛み”を見抜いて、
-
仮設スロープの提案
-
**中継置場(バッファ)**の設置
-
荷台の並べ替えやバンドのかけ直し
など小さな改善で1時間の遅れが0になる。改善の手応えがダイレクトです。
7|“ありがとう”が早く届く距離感
BtoBの仕事でも、親方や職長、監督からの即時フィードバックが日常。
-
「明日も同じ段取りで頼む」
-
「この置き方、めっちゃ作業しやすい」
その一言がやる気の源です。
8|キャリアの広がりが見える
-
現場リーダー:職長として工程・安全・品質を統括
-
機材スペシャリスト:荷揚げロボ/マテハン・各種資格を軸に
-
施工管理・倉庫管理:段取り力を活かして管理側へ
-
独立・請負:小隊を率いる“機動力”の商売も可能
“段取り×安全×信頼”はどの現場でも通用するポータブルスキルです。
9|デジタルで“待たせない”を実装
-
**到着予測(ETA)**を現場と共有
-
**電子受領(ePOD)**で数量・写真・位置を即時記録
-
フロア別の配置図をスマホで確認
紙と口頭だけの現場より、ムダ歩きが激減。身体も安全も守れます。
10|1日の流れ(例)️
-
朝礼・KY(危険予知)→搬入経路と合図者の確認
-
荷受け・仕分け→階別・部屋別にタグ付け
-
揚重・配置→先行スペースから順に“置き切る”
-
緊急差し込み対応→監督とスロット調整
-
終業前の整頓→翌日分の手前化(先置き・動線確保)
-
引き継ぎ→改善点を写真つきで共有
ケーススタディ:小さな工夫でチームの時間を救う ⛑️
状況:タワマンの内装期。石膏ボード900×1800が1フロア200枚、エレベーターは1基共有。
課題:搬入渋滞で大工が手待ち。
施策:
-
エレベーターの30分スロット予約
-
各戸の中継置場を設定し、先入れ先出し
-
通路の矢印養生+曲がり角の面当て
-
大工側と間柱建て込みの順番を擦り合わせ
結果:手待ちゼロ、1フロアの作業完了が前週比−90分。監督の工程も前倒しに。
新人さんへ:最初の90日で身につけたいこと
-
基本の持ち方・置き方:指を守る角度、コーナー保護、落下方向を作らない置き方
-
声と合図:短く、同じ言葉で。「止まれ」「上げる」「下げる」は全員同じ手で
-
道具の基礎:台車・ハンドリフト・ベルト・ラチェットの使い分け
-
養生の型:床・壁・角の三点セット、滑り対策
-
安全の優先順位:重い>高い>狭い。迷ったら“止める勇気”
できることが増えるほど、身体は楽に・現場は速く・信頼は厚くなります。
荷揚げの“やりがい”を支える3つの習慣 ✅
-
段取りはA4一枚に(時刻・経路・置場・連絡先)
-
写真で残す(ビフォー/アフター/不具合)
-
足場と足元を最優先(滑り・段差・転倒をゼロに)
結び——「荷を上げる」は、現場を前に進めること
荷揚げは単なる運搬ではありません。**時間を設計し、安全をつくり、作業者の生産性を最大化する“現場の推進力”**です。
今日もあなたが置いたその一山が、明日の施工を速く、楽に、安全にします。
静かな達成感と、たくさんの「助かった」を集めに、また現場へ。
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
秀英舎のよもやま話~“揚重を強くする”~
皆さんこんにちは!
株式会社秀英舎、更新担当の中西です!
~“揚重を強くする”~
人手不足、短工期、複雑化する現場。荷揚げはデジタル×標準化で一段ステップアップできます。ここでは、予約→入庫→縦横搬送→引き渡し→可視化まで、“摩擦を減らす”実装例を紹介します。
目次
1|配車DX:来る・積む・上げるが一気通貫 🚚📍
-
スロット予約アプリ:30分単位の受入枠。ジオフェンス通知で到着15分前に自動アラート。
-
電子伝票(QR):受付→ホイスト→フロア受渡まで1枚のQRで追跡。
-
混雑ヒートマップ:時間帯×ゾーンの待機分布を可視化→翌日リスケに反映。
💡 効果:待機▲30〜50%/問い合わせ電話▲90%/誤配ゼロ。
2|現場標準:だれが来ても同じ品質 🧱📘
-
ラベル規格:品名/階/ゾーン/重量/設置向き(⬆︎)をA6耐水で統一。
-
固縛テンプレ:本数・位置・締付順を品目別に図解。
-
合図カード:停止・巻上げ・徐行・非常停止の絵+短文を掲示。
-
動線カラー:縦=青/横=緑/危険=赤。テープとサインで迷わない。
📎 新人でも初日から回せる状態をつくるのが標準化の目的。
3|センサー&記録:壊れる前に止める 🛰️🧠
-
荷重ピン・傾斜センサーで過荷重・傾きをアラート。
-
風速・WBGT連動で運転中断基準を自動通知。
-
電子黒板:入庫→揚重→設置の写真を時系列保存、1年保管でトレーサブル。
4|KPIで回す“揚重ダッシュボード” 📊
-
平均待機時間/サイクルタイム/1便当たり積載率/破損率/歩行距離。
-
日次レポート:天候・人数・台数・遅延要因・改善点を1ページに。
-
週次会議:数字→原因→施策→担当→期限の1行フォーマットで意思決定。
5|“止めない仕組み”——BCPと近隣配慮 🧭🧯
-
迂回ルートと代替搬送(ホイスト停止時=ミニラフター/階段昇降機へ)。
-
停電・豪雨時の作業中断→再開手順をマニュアル化。
-
騒音管理:夜間は静音キャスター・防振マット・小声合図、掲示で近隣へ“今日は○階搬入”を告知。🔇
6|“30日で変える”改善ロードマップ 🗺️⚙️
-
Day1–7:受入スロット表・QRラベル・合図カードを導入。
-
Day8–14:固縛テンプレ&動線カラーを全フロアへ。
-
Day15–21:ダッシュボード稼働(待機・破損・積載率の3指標)。
-
Day22–30:ハイボリューム日の先出し棚+前夜仕分けでピーク平準化。
7|事例:14階建てマンション内装期のDX導入 🎯🏢
-
Before:朝の受入集中で1時間待ち、誤配と破損が散発。
-
施策:スロット予約、QR追跡、合図カード、先出し棚、夜間前仕分け。
-
After:待機▲46%/破損ゼロ/職長の移動距離▲31%/内装班の残業▲22%。
→ 仕上げ期の手戻りが激減し、引渡し前の“駆け込みストレス”が消失。✨
まとめ ✨
荷揚げ工事は、DX×標準化×安全設計で“待ち時間ゼロ・破損ゼロ”に近づけます。
予約→入庫→搬送→引渡→見える化を一本の線に。
「今の現場で何から?」に即答するなら、スロット予約とQRラベルから。私たちが導入から運用まで伴走します。📲🏗️💪
そして弊社では一緒に働く仲間も募集をしております♪
お問い合わせはお気軽に♪
![]()